四日市コンビナート(四日市市塩浜地区)がある場所に、かつて日本帝国海軍の第2海軍燃料廠があった(1941年開廠)。当時は日本の植民地だった台湾には、第6海軍燃料廠があり、その研究をしている台湾の研究者らが、調査のため来日し三重県を訪れ、4月25日、四日市市立博物館(同市安島)の学芸員やボランティアガイドから説明を受け、四日市空襲や第2海軍燃料廠の理解を深めた。
来日したのは、台湾の国立陽明交通大学の応用芸術研究所の賴雯淑(ライ・ウェンシュウ)教授ら6人と、津市出身でカナダ在住のアーティスト井早智代さん。賴教授は、日本軍の6つの燃料廠の当時の相互関係や運営概念を調査している。親交のある井早さんが津市出身であることから、調査活動の協力を依頼された。
四日市市立博物館では
最初に訪れた市立博物館では、第2海軍燃料廠関連の写真と戦争で焼け残った遺品などを見学し、森拓也学芸員から説明を受けた。賴教授は「写真や動画など多くの展示が見られ、丁寧に説明していただき、充実した時間だった」と話した。今後は、賴教授らの研究内容も同館で展示することを企画していくという。

【第2海軍燃料廠の配置図を見せながら解説する村田さん】
第2海軍燃料廠跡地では
午後からは観光ボランティアガイドの村田三郎さんの案内で、市立図書館(同市久保田)の地域資料室や、鵜の森公園(同市鵜の森)の四日市空襲殉難碑を見学した後、第2海軍燃料廠跡地の三菱ケミカル東海事業所の塩浜門に向かった。同燃料廠の初代燃料廠長の別府良三少将は、のちに第6海軍燃料廠の燃料廠長に就任している。そのつながりから2つの燃料廠は密接な関係にあったと言われている。
案内した村田さんは1967年から約40年間、同社(当時三菱油化のちに三菱化学)で勤務していた。当時、機銃弾痕と思われるものが残るコンクリート壁が敷地内にあったことを記憶している。この日は敷地の外で、賴教授らに第2海軍燃料廠の説明をした。村田さんは観光ガイドの時は夜景クルーズが人気があることから、夜景をテーマにコンビナートの解説をすることは多いそうだが、「今回の案内で、かつての四日市コンビナートの仕組みを思い出し、また自分が勤めていた会社の前で改めて戦争をテーマに話し、感慨深い」と話した。
通訳を務めた井早さんは「津市で生まれ育ち、祖父母がいた四日市にもよく来ていたが、四日市空襲や燃料廠についてほとんど無知だった。台湾の方の縁で、博物館の資料や村田さんのガイドを通し、戦前戦時中の人々の暮らしを学ぶことができて、感謝の念が大きい」と話した。
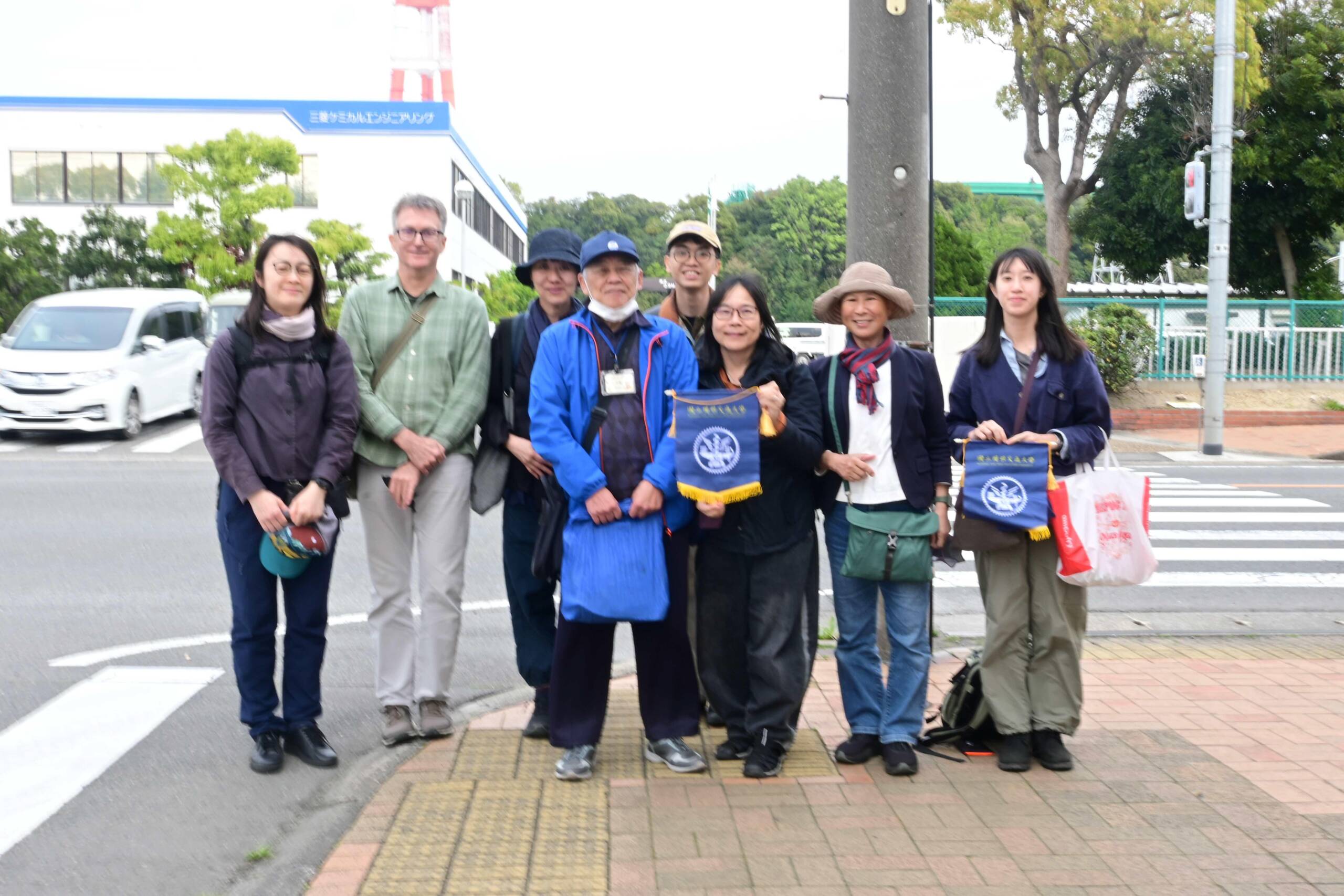
【村田さんと記念写真を撮る賴教授(前列右から3人目)と研究者ら】








